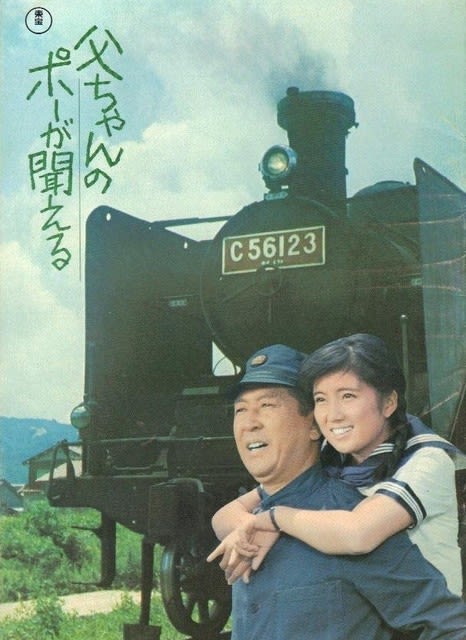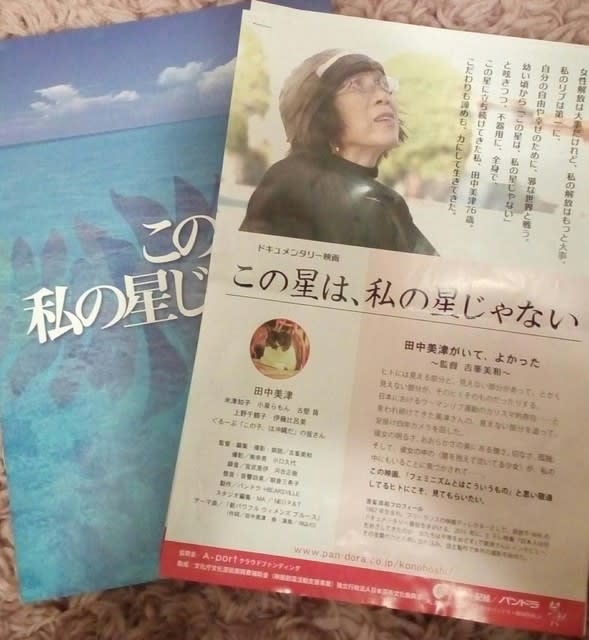1978年の映画だが、背景の時代の感じはもう少し前のように見える。
監督はイギリスのカレル・ライス、この人はイギリスのニューシネマの一人で、高校時代に『土曜の夜と日曜の朝』を見たが、あまりピント来ず、映画好きの先輩も「変な映画だったな」と言っていた。
だが、よく考えると日本の大島渚を代表とする松竹ヌーベルバークも、本家のフランスのヌーベルバークよりも、イギリスのニューシネマの方に近いと思える。
それは彼らの政治性で、フランㇲのヌーベルバーグにはほとんど政治的意識がないが、ニューシネマの連中にはあると思えるからだ。
彼らは、イギリスからアメリカに行って結構いい作品を作るようになるが、それは彼らに批判性があったからだと思う。
![]()
ベトナムのアメリカ人ジャーナリストのマイケル・モリアティが、一山当てようと麻薬を友人に頼んで、アメリカに運んでもらう。
この友人が元海兵隊員のニック・ノルティで、肉体派である。インテリのモリアティと肉体派のニック・ノルティで、『兵隊やくざ』の田村高広と勝新太郎を思わせる。
彼は、オークランド港で、軍艦に麻薬を隠して運びだし、モリアティの妻のチュズデイ・ウエルドの家に持ってくる。
だが、ウエルドは事情をほとんど聞いていず、ごたごたしている内に、家は二人組に襲われる。
一応FBI捜査官と言っているが、要は横取りしようとしている得体のしれない連中。
ノルティは、嫌がるウエルドを車に乗せて、サンフランシスコに行く。
そこは、まだフラワームーブメントで、チルドレンが花を売ったりしているが、時代的に少しずれているようにも思える。
子供を父親のところに預け、ノルティとウエルドは、山の元ピッピーが住んでいた集落のようなところに逃げる。
すると捜査官もやっって来て、彼らとの攻防になるが、モリアティは彼らに捉まっていて、麻薬との取引になる。
この集落が異様で、木造の小屋だが、舞台もあり、無数の電球が吊るされていて、昔は祭りをやったという。
今年、公開された『ワンス・アポン・ナ・タイム・イン・ハリウッド』のピッピー村みたいなものだ。
ノルティに言わせれば、「そこでは祭りをやっていて、歌い、踊った」という。
音楽は、全面的にクリーデンス・クリアウォーター・リバイバルで、『雨を見たかい』などが掛る。
最後、ノルティと捜査官連中との激しい銃撃戦になり、モリアティとウエルドは車で逃げ、ノルティも連中に勝つが、落ち合う場所の鉄道の線路に行くと、そこで死体になっている。
冗漫なところもあるが、時代的な意味も興味深い作品である。これらの成功の後、カレル・ライスは『フランス軍の中尉の女』で大成功する。
ザ・シネマ
![]()